
|
二荒山神社(日光)
●
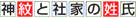
大中臣/宇都宮氏
(近世は輪王寺門跡が三山を総括した)
|
日光という地名の由来については諸説がある。観音菩薩の浄土を補陀洛山といい、その補陀洛山からフタラ山(二荒山)の名がついたという説、日光の山には熊笹が多いので、アイヌ語のフトラ=熊笹がフタラになりフタラが二荒になったという説、男体山、女峰山に男女の二神が現れたのでフタアラワレの山になったともいう。
いろは坂の入口付近に屏風岩があり、そこに大きな洞穴があり、「風穴」とか「雷神窟」などと呼ばれ、この穴に風の神と雷獣が住んでいて、雷をおこし豪雨を降らせ、春と秋に暴風が吹いて土地を荒したので二荒山という名ができたとも。
二荒が日光になったのは、弘法大師空海が二荒山(男体山)に登られたとき、二荒の文字が感心しないといって、
フタラをニコウと音読し、佳字をあてて日光にしたと伝えられている。
その始まり
日光の歴史は1200年以上まえの奈良時代、天平神護二年(766)に勝道上人が、四本竜寺を建てたのがその始まりという。勝道上人は奈良時代天平七年(735)、母の故郷である高岡の郷で生まれたと伝えられ、28歳のとき天平宝字五年(761)、下野薬師寺で試験を受け僧侶となったという。
天平神護二年(766)勝道上人は、大谷川の激流を神仏の加護を受けて渡り山内地区に草葺きの小屋を建て、毎朝、礼拝石に座り、二荒山の霊峰を拝していた。ある日、いつものように霊峰を拝していると、背後から紫の雲が立ち昇り悠々と大空に舞い上がって東北方面に吸い込まれていった。勝道上人はこの壮厳なる風景に心を打たれ、その地点に急ぐと、そこには紫雲石があり、勝道上人は青竜・白虎・朱雀・玄武の四神守護の霊地と感じ、この場所にお堂を建て「紫雲立寺」と名づけた。これが現在の「四本竜寺」と伝えられているものである。
時代は移り平安時代、真言宗の開祖といわれる弘法大師空海が、弘仁十一年(820)日光に来山、滝尾権現と寂光権現をまつられた。このとき空海は佳字を選んで「二荒」を「日光」に改められたと伝える。
さらに、嘉祥元年(848)には、比叡山の第三代天台座主の慈覚大師円仁が、仁明天皇の勅命をうけて日光に来訪。円仁は中禅寺に登り、神宮寺に七日間参護ののち、二荒山に登り一泊して下山、中禅寺湖を舟で巡って薬師堂を祀った。さらに、日光山内に三仏堂と常行堂・法華堂を建立した。
勝道上人の弟子たちは、円仁の徳を感じて天台宗に帰伏し、円仁の弟子と共に三十六ヶ坊を開いた。これが日光一山衆徒の始まりである。貞観二年(860)、勝道上人の従弟にあたる大中臣清真が、二荒山神社の神主となり、清真が日光山神主職の初代とされている。
仏教文化の栄えた鎌倉・室町時代には、数々の有名人、著名人が日光に参拝 していることが種々の記録から
うかがわれる。元暦二年(1185)、那須与一が日光権現・宇都宮大明神に祈願し、扇の的を射落とした。
永正六年(1509)、連歌師の柴屋軒宗長が来山し、「東路の津登」に院々僧坊およそ五百坊と記している。
ところが、天正18年(1590)小田原北条氏に加担したため、その滅亡とともに、豊臣秀吉によって所領を没収され、
以後、日光山は衰退していくこととなる。
中世から近世へ
江戸時代に至って、慶長十八年(1613)天海大僧正が日光山の住職となった。
天海は徳川家康に仕え、さらに、二代将軍秀忠・三代将軍家光にもに仕え、各将軍の家庭教師・政治顧問・相談役・黒衣の宰相として活躍したことはよく知られている。 天海は、家康より残された遺言によって東照宮の造営を差配。元和三年(1617)3月に完成、これが日光東照宮であることはいうまでもない。ちなみに、天海は寛永二十年(1643)江戸の東叡山において108歳で亡くなったと伝えられている。現代にも稀な長寿の人であった。
こうして日光山は、天海の活躍によって空前の繁栄をし、二十院八十坊、数百人の僧侶と社家、奉仕人で賑わうようになり、いまもその賑わいは衰えていない。 日光山では、天海の功績をたたえ「日光中興の祖」と称されている。
神職としては、初め大中臣氏が努めたが、平安期の前九年の役の際、石山寺の座主であった宗円が宇都宮に下って賊徒平定を祈った功により、初めて宇都宮社務となり、所在の神主らの上に座した。その子八田権守宗綱は社務と日光山別当を兼ね、孫朝綱のとき頼朝の御家人に列して宇都宮検校と称し両職を兼帯した。
しかし、宇都宮氏は武士として活躍することが多くなり、一山のことは神宮寺の満願寺座主の手に移った。
降って元和三年(1617)東照宮が造営され、さらに満願寺の後身光明院が輪王寺と改称されて、これが宮門跡となって
からは輪王寺・東照宮・二荒山神社の三つは一体となって門跡である天台座主が総裁し、明治維新に至った。
【丸の内一文字】
|
|


 [資料:日本史小百科「神社」岡田米夫氏著/国史大辞典ほか]
[資料:日本史小百科「神社」岡田米夫氏著/国史大辞典ほか]